2015年06月16日
釣り道具の名称
[タックル]とは?
▼仕掛けや竿、リールなどの釣り道具の総称です。このような道具を入れておく容器をタックルボックスと呼びます。
ロッド&リール
1. リール(ベイトかスピニングか?)
リール(糸巻き機)の代表的なものには二種類あり、一つはスピニングリールもう一つはベイトリール(キャスティングリールともいう)があります。
それぞれに長所短所があり、わかりやすく思い切って言うと初級者の方はずばり!スピニングリールの方を選んだ方が無難。大きな理由は一つ、「投げやすい」からです。遠くに飛ばせば良いというもではありませんが幅広く攻めるという理由においてスピニングの方が有利だからです。
対してベイトリールは糸よれが少なくラインの飛距離を調節したり大物がかかった時のラインのやり取りのしやすさ、また比較的重量のあるルアーの扱いに優れています。しかし、軽いルアーなどを遠くに飛ばすのが不得意で、扱い方に慣れるまでバックラッシュ(実際にラインが出ている量より勢いのついたスプール部分が回り過ぎてしまう為、糸フケが出て絡まってしまう現象)に悩まされることでしょう。これらの点を考え、長所短所を踏まえた使い分けをした使い方をオススメします。

2.ロッド
ロッドもリールと同じようにベイトロッドとスピニングロッドがあって、それぞれベイトリールとスピニングリールに合わせます。ロッドの固さや適合ライン、適合ルアーは表にしておきましたので御覧ください(製品により多少の仕様の違いがありますが、その場合は表示に従って下さい)。
|
ライン(糸)
近頃は化学技術が進み様々なラインが出ていますがここでは主なものだけを取り上げましょう。
1. ナイロン系
水に対して比重が軽くしなやかなことが最大の特徴。しかし、耐久性が他より劣って水となじみやすく、よれやすいのが難点でもあります。
2. フロロカーボン系
伸びが少なく、テンションがかかった状態でもパワーを発揮してくれます。しかし、ライン そのものが固い為リールに巻き取った際に乱れる性質があります。
3. PE系
比重が水よりも軽く伸びるということとは無縁の特殊ラインで、力強いフッキング(魚に針を引っかける瞬間)を可能にします。しかし非常に高価で、結び目の強度が非常に弱く結び方に手間がかかるのが難点です。ベイトリールには不向きだと言われています(しかし、一部には普通の結び方で良いとされているものもあります)。
ルアー
1. トップウォータープラグ
[ トップウォータープラグの種類]
ポッパー、ペンシルベイト、スウィッシャー、ノイジー、バズベイト・・・
 | ポッパー |  | ペンシル |
[ トップウォーターの狙い]
トップウォーターフィッシングは最もエキサイティングと言えるでしょう。トップウ ォーターとはその名の通りで水面付近でバスをヒットさせる釣りです。ですからフッキングする瞬間や、ルアーを追いかけてくるバスの姿が見えることもありルアーフィッシングの醍醐味を味わう事が出来ます。
[トップウォーターの使い方]
比較的活性の高い早朝や夕方に岸際、ウィード際などを攻めます。雨の日なども威力を発揮することでしょう。夜明け頃にフィールド到着する事が出来たのならなら、まず はトップウォータープラグをキャストしてみましょう。
アクション(動かし方)は、ポッパーならストップ&ゴー(動かして止める)が基本です。また、ペンシルベイトならルアーの頭を左右に振るよう(ドッグウォーク)にして誘うのも一つの手です。
2. ミノープラグ
[ミノープラグの狙い]
ハードルアー(ワームなどはソフトルアーという)の中では、最も小魚に似た自然な形をしたルアーでバスに対しても自然にアピールする事が出来るのが特徴です。同じミノーでもその種類は様々で、主に泳層によってフローティング、サスペンド、シンキングに分けられます。
特にルアーの動きを研究するのにはフローティングミノーは最適です。表層を泳ぐミノーを使いマスターすれば、技術はきっと他のルアーに応用出来るでしょう。
| [ミノープラグの使い方] フローティングはシーズンを選ばず使え、その名の通り表層近くで使用するため、根掛かりが少なく動きについても視野に入るので自在に操る事が可能です。サスペンドは中層、シンキングは深層用に用います。アクションは基本的にはストップ&ゴーですが、ひたすら早く引いてくるといった方法も時には効果的です。 時期と状況によりルアーの泳層を決め、その層を泳がせるようにリーリング(リールを捲くこと)しフローティングを使っている場合、もぐり過ぎたなと思ったらリーリングを止め少し浮くのを待ちます。 シンキングやサスペンドもその特徴に合わせてリーリング量を調節し、泳がせたい泳層をあくまでキープさせるのが肝心です。他にもトゥィッチングという小魚が逃げ惑う様子を演出するテクニックもあります。 |  |
3. クランクベイト
[クランクベイトの狙い]
ミノー系と基本的には動きは同じです。クランクベイトはそれぞれのリップの長さによって潜る深さが違い、また、リーリング(糸を巻く動作)を止めると水面に浮かんでくるかサスペンド(比重が水と同じに設計されている為、中層で漂うこと)するように設計されています。
| [クランクベイトの使い方] 上記の狙いを良く把握しフィールドの見える範囲で操作して試してみましょう。リーリングとストップの組み合わせがポイントです。ヒケツはリーリングした後きちんと一旦ルアーを止める瞬間を演出することです。というのも、バスは本来捕食が非常にニガテな魚で、きちんと食わせるタイミングをこちらで作ってあげなければ食いつけないからです。 リップの短い比較的フローティングタイプのものは、シーズンを選ばず使え表層に仕様するため、根掛かりが少なく動きについても視野に入るので自在に操る事が可能です。 サスペンドは中層、シンキングは深層用に用います。アクションは基本的に はストップ&ゴーです。また、ひたすら早く引いてくるといった方法も時に効果的です。時期と状 況によりルアーの泳層を決め、その層を泳がせるようにリーリング(リールを捲くこと)しフローティングを使って、もぐり過ぎたなと思ったらリーリングを止め少し浮くのを待ちます。 シンキングやサスペンドもその特性に合わせてリーリング量を調節し、泳がせたい泳層をあくまでキープさせるのが肝心です。 |  |
[バイブレーションの狙い]
|  |
5. ワーム
[ワームの種類]
ストレート、カーリーテール、パドルテール、クロー、リザード、チューブ・・・
[ワームの狙い]
今ままで述べてきたハード系プラグに比べ、よりリアルであつかいやすく、タフコンディション(釣れにくい時)でも、時と場合に関わらず対応できるのが特徴です。価格も手頃なのでハードルアーで攻めると根がかりしたりするようなところでも攻める事が出来ます。ただ、ゲーム性の高いルアーフィッシングの中では最も地味に見える釣り方かもしれません。
[ワームの使い方]
ワームのセットの仕方(リグ)にはいくつか種類がありますが、ここでは代表的 なものをいくつか挙げて説明しましょう。
 |  |
6. その他のルアー
・スピナーベイト
 | 形状から考えて、最も自然界にない形と動きなのに、なぜかよく釣れる。 バスの目にはどう映るのかは詳しく解明されていませんが、考えられるのはアピール力でしょ う。 金属で出来たブレードで水中に異音を発し、ラバースカートはヒラヒラと舞う。得体の知れない未知なものへの興味からかバスが追ってくる。摩訶不思議の世界、ぜひ一度お試し下さい! * ジグスピナー スピナーベイトの小型版と考えれば良いでしょう。 ただし、ラバースカートが付いていませんので、フックの部分にはお気に入りのワームをつけてたりして使います。 |
・バズベイト
 | スピナーベイトに似ていて、スピナーベイトの変形版と言えばいいでしょうか。 狙いとしては、スピナーベイトが様々なレンジ(泳層)を攻めるのに対してバズベイトはトップウォーター専門なのが特徴です。 水温が上がりシャロー(上層)にバスが浮いているような時には絶好です。 |
小物
プライヤー、ラインカッター、この2つは必需品で、無ければ色々不便があると思います。
フィールドで持ち運ぶ際も常に取り出しやすい場所に携帯しましょう。
 | プライヤー |  | ラインカッター |
タックルボックス
| ルアーや小道具を収納で大切なのはフィールドに出た時に身に付けて邪魔にならないように持ち運べるようなものがいいでしょう。 収納性の高い、色々なケースが入るベスト(プライヤーホルダーが外に付いているものがオススメ)やウエストバッグになるようなものがあれば良いでしょう。 小物ケースは、ポケットサイズのケースでベストのポケットなどに入れて持ち運べるので移動しながらの釣りには身軽で楽です。 2~4段式は、左の写真のような形態です。大きな収納力が魅力です。更に大容量の引出式もあります。しかし大型の物になると携帯性はないのでボートからの釣りなどに向いています。 携帯式は、ウエストバッグ式など様々な商品がでています。小物ケースと組み合わせて使える製品が便利です。 |  |
その他
その他にもせっかくの記録を計るメジャーや大物を釣り上げたのを友人などに自慢する為にカメラなんかあると良いですよ。
フィールドは景色もいいですしね。あとタオルも1枚は最低必要です、あれば何にでも使えますから。

2015年06月15日
ランタンの選び方
→ギリシア語で「輝く」という意味の「Lampein」が語源になっているようですね。
-------------------------
簡単に言うと、照明器具です。
-------------------------
野外生活では、日が沈むにつれ、徐々に周りが暗くなってくると、
サイト全体や夕食のテーブルを明るく照らすためにランタンを使用します。
夜の必需品となるランタンは、大きく分けで4種類に分かれます。
①電池式(LED、蛍光灯)
②ガス式(LPガスカートリッジ)
③液体燃料式(ホワイトガソリン、灯油)
④キャンドル式(ロウソク)
一般的には、サイト周りを明るく照らすことのできる「メインランタン」そして
テーブル周りを照らす「サブランタン」の2つが最低必要だと言われています。
「メインランタン」は広い範囲を照らす必要がありますので、光量の高い方が良いでしょう。
また、少し離れた所から照らしてくれるので、夏場なんかは虫を食卓に近づけさせない役割もあります。
ですので、
一番光量のある③液体燃料式ランタンを「メインランタン」として利用されている人も多いでしょう。
[メリット] ◎燃料費が安くなる、気温が低くても安定させることができる
[デメリット]▲手間暇がかかる(ポンピング、マントルのカラ焼き)
Coleman(コールマン)ノーススター チューブマントルランタン
⇒定価 17,500円(税込18,900円)↓
参考価格15,556円(税込16,800円)

※ここ数年①②でも光量のあるタイプの商品も発売されてきています。
自分の好みやスタイル、それぞれのシーンに合わせてお選びいただいても良いでしょう。
「サブランタン」はテーブルの上に置けるコンパクトなものが良いでしょう。
┗②ガス式がおススメです。(光量は明るすぎないように)
┗マントルを使用するタイプの方がやさしい光が灯ります。
[メリット] ◎取り扱いが簡単です。(初心者、めんどくさがりの方)
[デメリット]▲残量や気温によって火力が安定しない。
Coleman(コールマン)フロンティア PZランタン
⇒参考価格4,426円(税込4,780円)

最近では①電池式ランタンでも十分明るいものもございます。
例えば、こちら↓
GENTOS(ジェントス)LEDランタン EX-1000C
⇒参考価格7,306円(税込7,890円)

メインでもサブランタンとしても用途に合わせてオールマイティにご利用できます。
→光の色の変更そして明るさは無段階調整が可能!
※但し、コスト計算も忘れずに。。。
テント内は手軽で安全な③電池式ランタンに限ります!
Quechua(ケシュア)BL 100 V2 LANTERN ランタン
⇒参考価格1,780円(税込1,922円)

【独特のフォルムと置いてもぶら下げても使えるランタン!】
ムードあるやさしい光を楽しむには④キャンドルランタンも良いでしょう。
ロゴス(LOGOS)キャンドルランタン
⇒定価 880円(税込950円)↓
参考価格787円(税込850円)

その名の通りロウソクの光ですので、光量は少ないです。
防虫剤入りキャンドルを使うことで、夏場の虫よけにも便利です。
ランタンを選ぶ際には、バーナー類などの燃料と統一することで、効率よく消費できます。
それぞれ、長所や短所などの特徴を理解した上で選ぶとよいでしょう。
2015年06月10日
キャンプ用品基礎知識/ランタン編
 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2015年06月09日
キャンプ用品基礎知識/ツーバーナー編
 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2015年06月09日
グレゴリー/バックパック フィッティング
| |||||||||||||
| ||||||||
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015年06月09日
グレゴリー/テクノロジー
| パックの設計において、「いかなる使用状況下でも、常に快適な背負い心地と安定性が保たれる」というデザイン哲学をGREGORYが追求し続けて、すでに30年近く経ちます。アウトドアアクティビティーも多様化し、素材の軽量化が進む中、このデザイン哲学は変わらないまま、GREGORY独自の革新的テクノロジーがまた新たに加わりました。 |
| Wraptor™スタビライザー(特許申請中)は、激しい動きでもバックパネルが背面にしっかりと安定し、かつより効率のよい荷重移動を可能にするために開発されたグレゴリーの最新テクノロジーです。バックパネルのボトムにある左右のウイングのストラップを前方に引くと、バックパネルが腰から内方向へ引き寄せられ、パックが背面にしっかりと保持されます。また、バックパネルの折れを防ぎパックの荷重が簡便に、かつ広範囲に移動し、快適な背負い心地を実現します。(エスケープシリーズのアルペングロー、アンチグラビティーシリーズのGパック、スペクトラム、アドベントプロ、ウーマンズシリーズのアイリスに採用) | ||
| グレゴリー社が独自に開発した高密度ポリエチレン製の軽量で柔軟な熱成型フレームシートです。人間工学に基づいてデザインされたフレームシートが、背中の曲線に合わせて予めカーブし成型されているので、体の動きに柔軟に対応しかつ、しっかりと荷重を支えます。(アンチグラビティー、オールテレインシリーズの一部モデルに採用) | ||
| 高密度ポリエチレン製の軽量で柔軟な熱成型フレームシート(特許申請中)に、シングルアルミステイ、Auto-Cant™ハーネス、背面、ランバーの熱成型パッドを融合させた、グレゴリー社が人間工学に基づき独自に開発したExo-Frame™サスペンションシステムです。背中の曲線に合わせ予めカーブしたフレームシートと、軽量性と剛性を備えた中空のアルミ製ステイとの組み合わせにより、激しいアクションに柔軟に対応しかつ優れた荷重コントロールを発揮します。また、Auto-Cantハーネスシステムを組み込み、ハーネスは肩の動きに合わせて自在に対応します。(オールテレインシリーズのズール、エッコ、ヘイロウに採用) *ヘイロウにはステイはありません。
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年06月09日
グレゴリー歴史
| ウエイン・グレゴリーは14歳の時、ボーイスカウトの最高位に値する勲功記章(特別の功績に対して与えられる記章)プロジェクトの一環として、初めてバックパックを自作しました。それからまもなく、ボーイスカウトの地方大会で、カリフォルニア州、サンディエゴにあるアウトドア専門会社「アドベンチャー16」の創立者アンディー・ドロリンガーに出会いました。アンディーはウエインのデザインに感銘を受けました。それから2~3年の間、ウエインは「アドベンチャー16」の工場へ頻繁出入りして、そこで自作のための材料を揃えながら、バックパックのデザインをいろいろ考案しました。そして、ついにはこの若い会社で働くようになりました。 | |||
1970年、ウエインは先進のエクスターナルフレームパックの製造を目指し、彼の最初の会社「サンバード」を設立しました。その後、エクスターナルフレームパック自体の機能性に限界を感じ、1973年に会社を解散。当時新興のアウトドア産業において、ウエインは「アルペンライト」「ゲリー・アウトドア」「フロストライン・キット」「スノーライオン」など著名な多くのメーカーのスリーピングバッグ、テント、テクニカルウエアなどのデザインを、フリーランスとして手がけました。それから、ソフトパックの新しい動きとインターナルフレームという概念に彼の好奇心は傾き、自分が元々一番好きだったバックパックのデザインに戻ることを決心しました。そして、1977年、妻のスージーと二人で、グレゴリー・マウンテン・プロダクツ社を設立しました。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年06月03日
ラパラ歴史
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1905年 | ラウリ・ラパラ生誕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928年 | ラウリ・ラパラ結婚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930年代 | 漁のためにルアー作りをはじめる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929年からの「世界恐慌」もあり、暮らしは非常に貧しいものだった。 家族や生活の為、様々な工夫を漁に活かし、 嵐の中でもボートを漕ぎ続けるラウリの姿があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936年 | ファースト・ラパラの完成 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漁師生活から学んだ経験を生かし、コルクに銀紙を巻きつけた ファースト・ラパラの完成。驚くべき釣果をもたらしたこのルアーは、 オリジナルフローターの原型になった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939年 | ソ連×フィンランドの「冬戦争」勃発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦争により、コルクやバルサの調達が難しくなり、 松の皮でルアーを製作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940年代 | 兵役とラパラの能力の証明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウリ・ラパラ兵役に就く。 当時、前線の食料調達は、爆薬を用いての魚の捕獲が主だったが ラウリはルアーを用いて驚くべき漁獲量を証明。 兵役を終える頃には、この噂がフィンランド全体に広がる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルアー職人への道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噂が噂を呼び、ラウリの元にルアーの注文が殺到。 息子たちと共に本格的にルアーの生産がはじまる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952年 | ヘルシンキオリンピックと見本市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣り好きのアメリカ人選手が釣具店からラパラをお土産に購入。 同時期に開催された見本市での展示から評判になる。 これを機に様々な形で北米にラパラが浸透していく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959年 | ラパラ販売会社「ノーマーク社」の設立 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラパラに魅せられたアメリカ人バイヤー、ロン・ウェーバーらにより 「ノーマーク社」設立。代理店契約を結ぶ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962年 | 女優マリリン・モンローを特集した「LIFE誌」に ラパラの記事が同時掲載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知名度が飛躍的に伸び、300万個のバックオーダーを抱える。 第一次ラパラ・フィーバー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965年 | カウントダウン発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永久定番と呼ばれるカウントダウンの発表。 ラウリの四男カウコが水難事故で死去。 深い悲しみに暮れるラウリを、息子であるエスコ・リスト・エンショの 三兄弟が盛り立てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974年 | ラウリ・ラパラ死去 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982年 | シャッドラップ発表と第二次ラパラ・フィーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウリ・ラパラ最後の作品「シャッドラップ」発表。 35万個がソールドアウトし、100万個のバックオーダーを抱える。 品薄状態が続くと、湖畔のベイトショップでは有料で シャッドラップのレンタルが発生。 第二次ラパラ・フィーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999年 | ラパラ・ジャパン設立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000年 | VMC社吸収合併 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界的な伝統を持つフランスのフックメーカーであるVMC社を吸収合併。 これにより、飛躍的にラパラ純正フックの性能が向上。 (この吸収合併以前にBLUE FOXとSTORMを傘下におく) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年 | ラウリ・ラパラ生誕百周年とLR100発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウリ・ラパラ生誕百周年を記念して、ラパラ一族のみが 使うことを許されていたラウリの秘宝、LR100を限定発売。 エスコ・リスト・エンショが二色づつフェイバリットカラーを選び 各人のサインがプリントされている。全六色。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*この歴史年表は様々な資料に基づき作成しております。内容と異なる資料がございましたら ラパラ・ジャパン(株)までお申し付け下さい。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年06月03日
渓流釣りをはじめよう♪
 |  |
 | |
 | |
|
| ●渓流釣りとは | |
| 山奥の渓流に分け入って竿を出すのが渓流釣り。リールやウキなどは使わず、竿・糸・目印・ハリだけのシンプルな道具で渓流魚を釣り上げる「ミャク釣り」が一般的。釣り場では好き勝手に釣っていいというものではなく、ほとんどの河川は漁協の管理下に置かれている。各河川で定められたルール(体長制限、禁漁期間など)に従うこと。ポイントを変えながら上流へと釣り上がるのが基本だが、黙って先行者を追い越すのはマナー違反。渓流に棲むサケ科の魚たちは管理釣り場のそれとは違い、もともと警戒心が強い。ドカドカとむやみに川に立ち込んだりすると、魚を追い散らすことになるので注意。 | |
| 入漁券とは | 遊漁券ともいう。現在の河川では渓流魚を放流して魚影の維持に努めているところがほとんど。漁協は放流をおこなうかわりに入漁料を徴収するシステムになっている。その日だけ使える日券と、期間内に何回でも使える年券とがある。入漁券は川沿いの釣具屋や雑貨屋などで販売されているが、早朝にはお店が開いてないこともあるので注意。日券は現場で監視員から購入すると割高になることが多い。 |
| 渓流釣りのターゲット |
 |  |  | ||
| ■ヤマメ | ■アマゴ | ■イワナ | ||
| パーマークと呼ばれる小判型の模様が銀白色の魚体に映える渓流の女王。静岡県以北の太平洋側や日本海側、北海道、九州などに分布。海へ下って大きくなったものが鱒ずしで有名なサクラマス。つまりヤマメはサクラマスが渓流に居残ったものだ。渓流でよく釣れるのは20cm前後。 | 中部、関西の太平洋側や瀬戸内海沿岸、四国、九州の一部に分布するのがアマゴ。ヤマメとそっくりだが体側に朱点があるのが特徴。海に下って大きくなったものはサツキマスと呼ばれる。 | 河川の最上流部に棲むのがイワナ。体側に散らばる薄い斑点が特徴だが、色など個体差が激しく分類が難しい魚。よく釣れるのは25cm前後。海に下って大きくなったものはアメマスと呼ばれ、北海道や東北などで見られる。 |
 |
|
| ||||||||||||||
| エサいろいろ |
| ||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||
| SMG-20 KOH Ti(コーティーアイ) フライフィッシャーに最もオススメなのが、これ!帽子を深く被っていても、ストレートテンプルなので着脱が容易で、こめかみが痛くならず、パイロットグラス風なのがプロっぽくてカッコイイ。 | CA-019C ネクサス ゴアウィンドストッパー シェルシマノキャップ(ツバワイドタイプ) 防水・透湿、撥水性のあるゴアウィンドストッパーシェルを採用した『シェルシマノキャップ』。ワイドなツバは偏光グラス装着時に絶大な効果を発揮します。カラーはシルバーで熱を吸収しにくく通年使用できるオススメのアイテムです。 | |||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||
| スパッタッシュメッシュ防蚊ジャケット JA-001D | 撥水フィッシングベスト VE-034D | |||||||||||||||||||||
| 抜群の収納力を発揮する多数のポケット、快適性を高めるベンチレーション。袖のロールアップで、ベーシックデザインでありながら、機能性を高めたフィッシングシャツ。 | 基本機能を備えた汎用性の高いシンプル撥水ベスト。肩部は着心地を考慮したクッション仕様。背中上部にネットホルダーとして使用可能なD環付。 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||
| シマノ エアサーモベイト ステンXT CS-030C | ダイワ タックルベルト II | |||||||||||||||||||||
| グリップでベストのエサ箱ホルダーやベルトに装備出来るため身動きが取り易く大変便利です。何より脱着可能な防水小物ケース(スタッフケース)が付いてるため便利さに便利さが加わったおすすめの一品です!! | ||||||||||||||||||||||
| ウェーダーの基礎知識 |
|
 |

|  
| ||||||||||||
 |
| ■アタリとアワセ |
 |
|
 |
 | |||
|
| ■塩焼き■ | ■刺身■ | |||||||||||||||||||||||
 |  | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
2015年06月03日
リバレイ~フローターヒストリー
          |
|








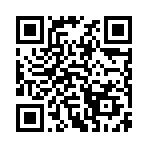























































































 スキッターポップで海面爆発を楽しんだ後には、水面直下を潜行するLCシリーズの出番です。
スキッターポップで海面爆発を楽しんだ後には、水面直下を潜行するLCシリーズの出番です。 CDってルアーは、実に応用範囲が広い。トップからボトムまであらゆるレンジを探れ、スローからファストまでスピードレンジの幅も広い。ある漁師が死んだイワシと死んだシイラの沈下速度は同じだと言っていました。実はCDの沈下速度は死んだ魚の沈下速度に極めて近いのです。シーバスライブの撮影場所を決める時、シーバスが居るかどうか?探る為に僕は毎回CDをカウントダウンさせていました。
CDってルアーは、実に応用範囲が広い。トップからボトムまであらゆるレンジを探れ、スローからファストまでスピードレンジの幅も広い。ある漁師が死んだイワシと死んだシイラの沈下速度は同じだと言っていました。実はCDの沈下速度は死んだ魚の沈下速度に極めて近いのです。シーバスライブの撮影場所を決める時、シーバスが居るかどうか?探る為に僕は毎回CDをカウントダウンさせていました。 SeaBassLiveⅠ「真実は水の中」で、同じルアーに同じシーバスが三回も違った形でアタックすると言う、劇的なラストを飾ってくれたのが、このテールダンサーです。
SeaBassLiveⅠ「真実は水の中」で、同じルアーに同じシーバスが三回も違った形でアタックすると言う、劇的なラストを飾ってくれたのが、このテールダンサーです。











